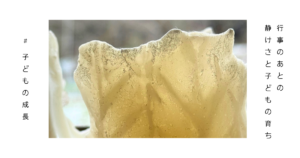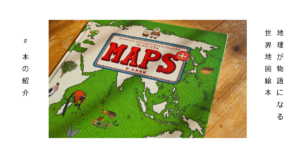「お友達を家に呼んだのに遊ばない…」 そんな様子を見ると、つい「どうしたのかな?」と心配になりますよね。 でも実は、それも子どもが成長しているサインなのです。
今回は、「遊ばない」子どもの行動をどう受け止めればよいか、そしてどのように関わると良いのかを、発達の視点からお伝えします。
「遊ばない」のは悪いことじゃない
3歳くらいまでの子どもにとって、「お友達を家に呼ぶ」ということ自体が、すでに大きな出来事です。 「お友達を呼びたい」という気持ちは、心の中に「社会の芽」が育ちはじめた証拠。 呼んで満足してしまうのは、それだけで心の世界がいっぱいになるからです。
大人のように「来たら一緒に遊ぶ」という発想は、まだ生まれていないだけ。 子どもたちは、少しずつ人との関わり方を学んでいく途中にいるのです。
どう関わればいい? 年齢別の見守り方
3歳ごろまで 安心できる場をつくる
3歳以下の子どもの場合、無理に遊ばせようとしなくて大丈夫。 「〇〇ちゃんが来てくれたね」「一緒にいるね」と、いま起きていることをそのまま言葉にして伝えるだけで十分です。 それが子どもの中に「気づき」の灯をともします。
もし子どもが戸惑っているようなら、親がまずお友達と少し遊んでみて、そこに自然と自分の子を巻き込んであげましょう。
4歳ごろから 相手を意識する心を育てる
4歳くらいになると、相手の気持ちを少しずつ想像できるようになります。 そんなときは、「〇〇ちゃんはどう思ってるかな?」「一緒に遊ぶならどんなおもちゃがいいかな?」と声をかけてみましょう。 「相手を思いやる力」が、こうしたやりとりの中で育まれていきます。
「遊ばない」=成長していない、ではない
子どもが遊ばない姿を見て焦ってしまうのは、子どもを大切に思うからこそ。 でも、子どもにとっては「一緒にいられること」そのものが、もう十分に満足な時間なのです。 静かに隣に座っているだけでも、心の中ではたくさんの学びが起きています。
「遊ばない」という行動も、心の成長の一段階。 今日も、安心して見守ってあげましょう。
まとめ 関わらない時間も、育ちの一部
・「遊ばない」は、発達の自然なプロセス
・3歳前後では「呼んで満足」が普通
・親が焦らず、いまの子どもをそのまま受け止めることが大切
関わらないように見える時間の中でも、子どもたちは「社会の芽」を静かに育てています。 親のあたたかいまなざしこそが、子どもの心を安心で包み、次の一歩を導いてくれますよ。