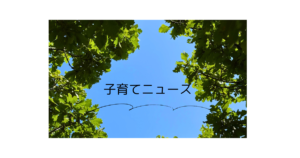おもちゃを取り合う子どもたちに「かわりばんこだよ」と言っても、なかなかうまくいかない——そんな経験はありませんか? でもそれは、子どもがわがままだからではありません。
じつは「かわりばんこ」には、「未来を想像する力」が深く関係しているのです。
3歳までは「今、この瞬間」に生きている
小さな子どもにとって、「順番を待つ」という行為はまだ少し難しいことです。 なぜなら、3歳くらいまでは「今ここ」に全力で生きているから。
未来を想像したり、「あとで自分の番がくる」と理解する力は、発達の途中にあります。 だから、いま目の前にあるおもちゃを離すことが難しいのです。これは自然な成長の段階であり、叱るべきことではありません。
「待つ力」は日々の小さな工夫から育つ
「かわりばんこ」を覚えるのに必要なのは、我慢を強いることではなく、「見通しを持てるように助けてあげること」です。 以下のような小さな工夫を取り入れてみましょう。
- 歌を使う 「この歌が終わったらかわりばんこね」と伝える。
- 砂時計を使う 「砂がぜんぶ落ちたら次は○○ちゃんの番」と見える形で伝える。
- 気持ちの切り替えを助ける どうしても待てないときは「ポケットの中に何かあるか見てみよう」と誘う。
こうした小さな工夫を通して、子どもは少しずつ「順番を待つ」ことを体験として学んでいきます。
「できない日」もあっていい。成長はゆっくりで大丈夫
大人の目から見ると、「昨日はできたのに今日はできない」と思う日もあります。 でも、それが自然です。
子どもたちは、行ったり来たりしながら少しずつ社会的な力を身につけていきます。
うまくいかない日も、焦らずに見守ってあげましょう。 「今を生きる」子どもたちにとって、順番を待つことも、成長への大切な一歩です。
まとめ 「かわりばんこ」は、子どもが社会と出会う最初の扉
子どもが順番を守れないとき、「ダメ」と言いたくなるかもしれません。 でも、その背後には発達のペースと小さな努力があります。
今日うまくいかなくても大丈夫。 子どもはちゃんと育っています。 あなたの笑顔と見守りが、子どもにとっていちばんの「道しるべ」になりますよ。