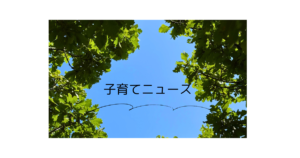約束を破ったり、あえて「しない」を選んだり。心がつまる場面の裏側には、子どもの成長の芽があります。シュタイナー教育の視点も踏まえながら、親が今できる具体的な対応をまとめました。
反抗は「悪さ」ではない——まずはその意味を知る
8歳ごろから、子どもは「自分で決めたい」という欲求を強く持ち始めます。大人から見ると不可解な「約束を破る」「あえてしない」といった行動は、親を困らせようとする悪意ではありません。むしろ自我が育ち、自分の意志を試している成長の一端です。
シュタイナー教育でも、自我の芽生えや自己主張は発達の重要な段階と捉えられます。ここで大切なのは、叱って抑え込むのではなく、その芽を丁寧に扱うことです。
なぜ「禁止」だとうまくいかないのか
「ダメ!」と禁止すると、子どもの注意はその「禁止された行為」に集まりがちです。「してはいけない」と言われてはじめて意識が向き、興味が増すこともよくあります。結果として指示と逆の行動をとりやすくなります。
許可と選択肢で向き合う具体的な方法
禁止ではなく、「許可・情報・選択の枠」で伝えることが有効です。いくつかの実例を紹介します。
- 許可の例
「走らないで!」→「歩いていいよ」 「持ち帰らないで!」→「ここに置いておいていいよ」 - 情報と選択肢を渡す
たとえば長靴を履かせたいときは、いきなり命令するのではなく
「外は雨だよ」→「長靴? 合羽?」と聞いて、子どもが自分で選べるように導きます。
選べる余白を与えることの効果
小さな余白を渡すことで、子どもは自分で考え、責任を引き受ける練習ができます。
すべてを完璧にこなせる年齢ではありません。試行錯誤を温かく見守ることが、最終的に自律した子どもを育てます。
まとめ
約束を破る行動は、叱るべき「悪さ」として受け取るのではなく、「自分で決めたい」という成長のサインとして受け止めましょう。禁止の代わりに許可や選択肢を渡すことで、子どもは考え、責任を学ぶことができます。