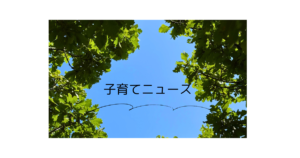2025年、日本でデジタル教科書が正式に導入されます。 新しい時代の教育が始まる一方で、「子どもの学び」は画面の中だけで育つのか?という問いも生まれています。 今回は、国内外の教育動向と、シュタイナー教育の視点から「これからの学び」について考えてみましょう。
2025年、日本でデジタル教科書が正式に導入
2025年9月、中央教育審議会がデジタル教科書を正式な「教科書」として位置付ける審議まとめを了承しました。 英語を皮切りに、今後は算数や理科など主要科目にも拡大予定です。
制度改正により、紙とデジタルの併用(ハイブリッド)が基本方針となり、各学校や学年に応じた運用が段階的に実施されます。
海外では「紙に戻す」動きも
一方で、海外ではデジタル学習の見直しが進んでいます。 スウェーデンやノルウェーなどの教育先進国では、読解力や集中力の低下が指摘され、紙の教科書に回帰する動きが出ています。
日本国内の研究でも、長時間のデジタル機器使用が学力や集中力に影響する可能性があると報告されています。 とはいえ、協働学習や個別学習に上手に活用すれば、学びを深めることもできるとされます。
「どれを使うか」よりも「どう使うか」
大切なのは、紙かデジタルかを選ぶことではなく、「どう使うか」「どう感じるか」という視点です。 便利さや効率の追求だけでなく、子どもがどんな気持ちで学びと向き合うのかを大切にしたいところです。
シュタイナー教育に学ぶ「自分でつくる学び」
シュタイナー学校には、そもそも教科書がありません。 子どもたちは白いノートに絵や文章を描きながら、自分だけの学びの本をつくっていきます。
それは、外から与えられた知識を写すのではなく、内側から生まれる発見を形にする時間です。 紙でもデジタルでもない、「その子自身の中にある教科書」を育てることこそ、これからの時代に必要な学びかもしれません。
家庭でできる「学びの芽を育てる会話」
たとえば、子どもが学校から帰ってきたとき、 「今日、どんなことが楽しかった?」 そう一言聞くだけで、子どもの中にある学びの種が芽を出します。
親子の会話は、どんな教科書やデジタルツールよりも豊かな学びを生む時間。 未来の学びは、そんな小さな時間から育っていくのかもしれません。
まとめ 学びの本質は「自分で感じる力」にある
デジタルでも紙でも、最も大切なのは「感じる力」や「考える時間」をどう守るか。 シュタイナー教育のように、子ども自身が発見し、表現していく学びが、これからの教育の鍵となるでしょう。
便利さに流されず、子どもの中にある「学びの教科書」を、これからも育てていきたいですね。