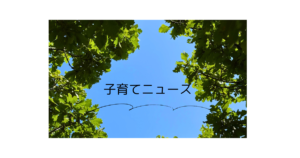叱ったら一瞬は静かになっても、またすぐに爆発……。それは落ち着いたのではなく、びっくりして固まっているだけかもしれません。
今回は、シュタイナー教育の視点を踏まえつつ、言葉で諭すよりも「体の感覚」へやさしく働きかけて癇癪を和らげる方法を紹介します。
なぜ「叱る」だけでは落ち着かないの?
癇癪の最中、子どもの神経は高ぶり、理屈や説得は届きにくい状態です。
大声や厳しい言葉は、さらに緊張を高めがち。 表面的には静まって見えても、内側の不快は残るため、時間が経つとまた噴き返してしまいます。
「感じる体験」で内側から静けさをつくる
言葉で頭に働きかけるよりも、体の内側の感覚に意識を向けられる体験が効果的です。
体がゆるむと、心も自然に整います。
すぐできる具体策3つ
1. コップ一杯の水を「ゆっくり味わう」
- 静かな声でコップを手渡し、「一緒にゆっくり飲もう」と寄り添う。
- 冷たい水が口から喉、胸へと流れる感覚を、親も同時に感じてみる。
- 数口でOK。「どう?」と答えを求めず、沈黙ごと受けとめるのがコツ。
2. 小さなスキンシップで「安心」を思い出す
- 頭をそっとなでる。肩に手を置く。背中に手のひらを当て、呼吸に合わせて数回ゆっくり押す。
- 言葉は最小限。「ここにいるよ」「大丈夫」など短く、穏やかに。
3. 手を使う小さな遊びでエネルギーを転換
- 指あそび、タオルを握って離す、深呼吸に合わせて手を開閉……席を立てない場でもOK。
- 「10までいっしょに」「砂が落ちたらおしまい」など短い区切りで。
まとめ 叱る前に、感じる体験を手渡そう
- 叱って静まるのは「フリーズ」。本当の落ち着きではない。
- 体の内側の感覚(水・触覚・呼吸)に寄り添うと、心も自然に整う。
- 短く、ゆっくり、同じリズムで。落ち着いた後にルールを確認。
まずは次の癇癪で「お水を一口」「背中に手」を意識してみましょう。
やさしい体験が、子どもの安心と安定につながります。