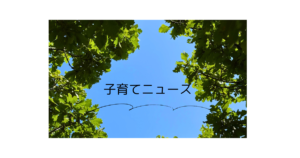「早くして」「なんでできないの」──子育ての中で、思わず口にしてしまう言葉。けれどその奥には、「この子、大丈夫かな」という小さな不安があるのかもしれません。
シュタイナー教育では、「自立」は子どもが自ら「やってみたい」という喜びから育つと考えます。この記事では、日常の中で使える小さなコツを通して、子どもの自立を応援するヒントを紹介します。
子どもの「できない」は、責めるより理解する
「できない」ことは、子どもにとって「成長途中」のサインです。大人が焦る気持ちは自然なものですが、焦りや不安をベースにした声かけは、子どもの心を固くしてしまうことがあります。
「早く」「自分でして」と言う前に、まずは子どもの今の姿を見つめましょう。「できない」ではなく、「これからできるようになる途中」と捉えること。それが自立の土台になります。
「やってみたい」を引き出す言葉がけのコツ
子どもが意欲を持つためには、「楽しそう」「自分にもできそう」という感覚が大切です。たとえば──
- 「お母さんみたいに料理してみる?」
- 「洗濯したら虹みたいに干そうよ」
- 「明日はボタンを一緒につけてみようか」
そんな言葉がけは、義務ではなく「遊び」としての学びにつながります。子どもは「やらなきゃ」ではなく「やってみたい」と感じたとき、自然に成長のスイッチを入れるのです。
「できない日」があっても大丈夫
どんなに前向きな声かけをしても、うまくいかない日もあります。でもそれでいいのです。大人だって、毎日完璧にはできません。
大切なのは、「また今度やってみようね」という安心感を伝えること。小さな積み重ねの先に、子どもは確かな自信を育てていきます。
歯みがきができたらキャンプに行ける、料理ができたらみんなでピクニック──そんな小さなワクワクを結んでいけば、自然と自立の芽は育ちます。
シュタイナー教育に学ぶ「自立」の本当の意味
シュタイナー教育では、「自立」とは単に自分でできるようになることではなく、「自分で感じ、考え、行動できる人になる」ことだと考えます。
そのためには、親が信じて待つ時間が欠かせません。子どもが失敗したときも、それを「ダメなこと」とせず、「学びの途中」として受け止める視点が、子どもの内側にある力を育てます。
まとめ あたたかい未来を言葉でつくる
「できない」から「やってみたい」へ──その一歩をつくるのは、大人の言葉の中にあるあたたかい未来です。
今日の何気ないひとことが、子どもの「できた!」につながるかもしれません。焦らず、比べず、ゆっくりと一緒に歩んでいきましょう。