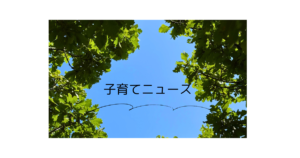子どもにネット検索やAIをどう使わせたらいいのか。
すぐに答えが出る便利さと、子どもの成長に必要な「わからない時間」。
今回は、シュタイナー教育の視点も交えながら、子どもとITの関わり方について考えていきます。
なぜ「わからない時間」が大切なのか
検索すればすぐに答えがわかる時代。
「わからないことは気持ち悪い」「調べればすぐに解決できる」という考えが当たり前になりつつあります。
しかし、子どもにとってはこの「すぐに答えが出る」環境が、本来の思考や感性の成長を妨げることもあります。
本当に大切なのは「わかりたいけど、まだわからない」という時間。問いを胸にとどめて思いをめぐらすことが、心の深みや柔軟な思考を育てていきます。
ネット検索やAIとの向き合い方
子どもとITの関係は、使うか使わないかという二択ではありません。
大切なのは「どう付き合うか」。
AIやネットを通して便利さを知る一方で、「わからない時間」を奪いすぎないように、親が意識的にバランスをとることが求められます。
日常でできる「わからない時間」の育み方
- 物語を読む時間を大切にする:本を読むことは「すぐに答えが出ない問い」と出会う時間です。
- 会話の中で問いを共有する:「どうしてだろうね」「ふしぎだね」と一緒に考え、結論を急がない体験が深い余韻を残します。
- 自然に触れる:空や星、草花など「すぐに答えの出ない不思議」に出会うことで感性が耕されます。
まとめ 「まだわからない」を抱えられる力
子どもの成長において、本当に大切なのは「まだわからない」を心にとどめられる力です。
それは人間としての深みやしなやかさにつながり、人生を豊かにしていきます。
ネット検索やAIの便利さを知る時代だからこそ、子ども時代には「わからない時間」をたくさんプレゼントしてあげたいですね。