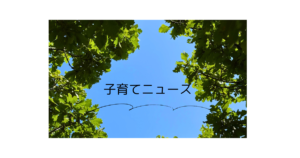「順番を待てない」「電車でそわそわ」——それは、わざとでも反抗でもありません。子どもは、心とからだの器がまだ育ち途中。叱るよりも、動きたいエネルギーを上手に“遊び”へ導くヒントをまとめました。今日からお出かけが、少しやさしく、少し楽しくなりますよ。
じっとできないのは自然な発達
子どもが落ち着かないと、親は「言うことを聞いてくれない」と感じがちです。でも 6歳くらいまでは、長い待ち時間や座り続けること自体が難しいのが自然な姿。 能力の不足ではなく、発達のプロセスだと理解できると、関わり方がやわらぎます。
叱るより、エネルギーを「導く」
「静かにして」「動かないで」と押さえるほど、子どもの内側のモーターはうなります。コツは、 動きたい・関わりたいエネルギーを、場に合った活動へ乗せかえること。
お店のレジ待ちで
- コックさんごっこ:カゴの材料を見せて「今日のメニューは?」と会話を広げる。手で野菜を切るまねなども効果的。
- 食材さがしゲーム:「赤いものを3つ見つけよう」「丸いものはどれ?」と観察を遊びに。
電車・バスの中で
- 車掌さんアナウンス:「次は何駅?」窓の外の目印を見つけて一言アナウンス。
- かぞえてみよう:「見える家は何軒?」「青い看板はいくつ?」視線を景色へ。
「手がうずうず」する時に
- 手遊び・あっち向いてホイ:立てない場所でもOK。小さな動きで充足感を。
- ミニ視覚タイマー:砂時計やタイマーで「砂が落ちたら座るね」と静かな合図に。
やさしい境界線の作り方:短い言葉+具体的な提案
禁止の重ねがけより、短く具体的な提案が効きます。例えば、
- 「声は小さく、手はひざに。次の駅まで車掌さんね」
- 「列ではお母さんの手を持って、赤いものを探そう」
してほしい行動を一つだけ伝え、できたらすぐに、「できたね」「助かったよ」。
成功体験が次の意欲に火を灯します。
準備で8割決まる:外出前のミニセット
- 小さなお仕事:「きっぷ係」「買い物リスト係」など役割を一つ。
- 手のアイテム:ポケットサイズの絵カードや指人形、短い手遊びリスト。
- 合図の約束:「砂が落ちたら座る」「3つ数えたらおしまい」—出発前に共有。
まとめ エネルギーは敵ではなく味方
- 6歳ごろまでは「じっと」を求めすぎず、発達のプロセスと理解する。
- 叱るより、場に合う“遊び”へエネルギーを乗せかえる。
- 短い言葉+具体の提案、できたらすぐ褒める。
- 視覚タイマーや役割づくりなど、外出前の準備でスムーズに。
じっとできないのは、まだ育っている途中だから。
エネルギーを遊びに変えられた日、親子の時間はもっとやさしく流れます。