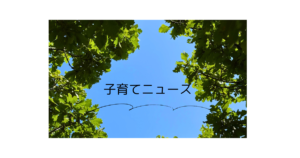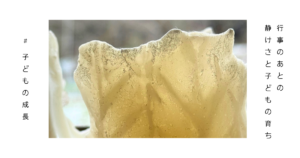テレビやタブレットが当たり前になった今、子どもが「耳をすます時間」はどれほどあるでしょうか?
シュタイナー教育では、絵本を見せずに「語る」時間をとても大切にしています。今回は、子どもの耳を育てる意味と、家庭でもできる実践法をご紹介します。
「耳を育てる」とはどういうこと?
現代の子どもたちは、視覚情報に囲まれて日々を過ごしています。その中で、耳で物語を聞き、想像の世界を広げる機会は減少しています。
しかし、音だけで物語を受け取ることで、子どもは自分の頭の中に情景を描き、登場人物の気持ちを感じ取ろうとする力が養われます。
シュタイナー教育が大切にする「素話」の時間
「素話(すばなし)」とは、絵本を読まず、語り手の声だけでお話を伝える方法です。お話の世界に耳からじっくりと入るこの時間は、子どもの内面を豊かにし、感受性や集中力、そして共感力を育てます。
実際、教室でも最初は落ち着かずにそわそわしていた子が、回数を重ねるうちに目を輝かせて耳を傾け、最後には「もっと聞きたい」と言うようになります。
おうちでできる実践法
- 1. 自分の子ども時代を語る
「ママがね、あなたぐらいのころ……」といった昔話は、子どもにとって特別なお話になります。 - 2. わらべうたや詩を取り入れる
短くてリズミカルな言葉は、耳に心地よく残り、記憶や安心感にもつながります。 - 3. 夜寝る前の5分だけ語る
絵本を読まなくても、短いお話を語るだけで十分効果があります。日々の暮らしに取り入れてみてください。
耳から育つ想像力と共感力
音だけで世界を感じる体験は、単なる知識の蓄積ではなく、子どもが“感じる力”を育てます。想像力を使って情景を描いたり、登場人物の気持ちを思いやったりする中で、人の心に寄り添う力が自然と育まれていきます。
まとめ 耳をすます時間は、心を育てる時間
シュタイナー教育に学ぶ「耳を育てる」取り組みは、特別な道具も教材もいりません。大切なのは、大人の声と、子どもに語りかけるほんの少しの時間です。今日から、親子で静かな語りのひとときを始めてみませんか?