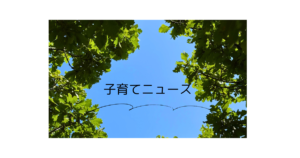「ごほうびをあげないと、やる気を出さないかも…」
そう感じたことはありませんか?でも実は、ごほうびは逆効果になることもあります。
この記事では、子どもが本当にやる気を育てていくために必要な関わり方をお伝えします。
「ごほうび」の落とし穴とは?
ごほうびは、一見やる気を引き出す便利な方法のように思えますが、実は長期的にはマイナスの影響があることが多くの実験で明らかになっています。
たとえば、テレビゲーム好きの子どもたちを対象にした実験では、ごほうびがあるグループはゲームをやらされているように感じ、時間が来るとすぐにやめてしまったそうです。一方、ごほうびのなかったグループは夢中になって遊びつづけました。
この実験が示しているのは、「ごほうびが目的になると、楽しさが消えてしまう」ということです。
ごほうびがないとやらなくなる、より多くを要求する、最低限しかやらなくなる…という負のループに入ってしまうこともあります。
日常で気をつけたいこと
もちろん、子どもが頑張ったあとにちょっとしたプレゼントをあげるのは悪いことではありません。でも「やったらあげる」という条件付きのごほうびは、習慣にしないように気をつけましょう。
大切なのは、「やること自体が楽しい」と感じられる工夫です。
子どもが「できた!」と感じた瞬間に、親が一緒に喜んであげること。それだけでも子どもの内側からわきあがるやる気は育っていきます。
子どもの「やりたい」を育てる関わり方
子どもが自然と行動したくなるとき、それは親のまなざしが温かく、見守られているという安心感があるときです。できることを一緒に喜び、失敗も受けとめてもらえる環境が、子どもにとって何よりのモチベーションになります。
子どもが「またやりたい」「もっと工夫したい」と思えるような言葉かけや環境を整えていくこと。これはごほうび以上に深く子どもの心に届きます。
まとめ
子どもにやる気を出してほしいと願うのは、親として自然なことです。でも、そのために毎回ごほうびを使ってしまうと、本来の楽しさや達成感を奪ってしまうことも。
ごほうびがなくても、子どもは育つ。そう信じて、子どもの心の動きに寄り添っていけたらいいですね。