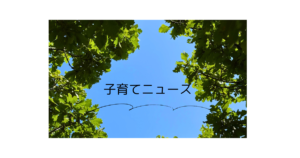絵本を散らかしたり、触ってほしくないものに手を伸ばしたり…
小さな子どものいたずらに困った経験はありませんか?
実はその行動、叱るべきことではなく「成長のサイン」かもしれません。
この記事では、いたずらの裏側にある子どもの心理と、やさしく寄り添う声かけのコツをご紹介します。
「またいたずら…」とため息が出る前に
ちらばった絵本を見て「またやってる…」とため息をついてしまうこと、子育て中なら誰にでもあること。
でも、2歳や3歳の子どもにとって「ダメって言われたからやらない」という理屈は、まだうまく働きません。
「やりたい!」という気持ちが先に出てしまい、叱られたことを思い出す力も未発達なのです。
いたずらは「今」を一生懸命生きるサイン
子どもは、大人が思うよりもずっと「今」を一生懸命生きている存在。
だからこそ、その瞬間の衝動に従ってしまうし、同じことを繰り返してしまいます。
大人のルールとは違う時間軸で生きている子どもたちに、まずは気持ちを寄せてみましょう。
叱る代わりの声かけ例
例えば、本棚から絵本がすべて出されていたら、まずはその状況を実況中継のように伝えてみましょう。
「本がたくさん出てるね」
そのあと、こう声をかけてみてください。
「どうしたら、この本たちがお家に帰れるかな?」
まるで冒険に出た仲間たちをお家に戻すように、子どもは一冊ずつ絵本を大切に片づけ始めるかもしれません。
子どもを責めず、行動を育てるチャンスに
子どもが本を片づけられたら、こんな言葉をかけてあげましょう。
「ありがとう。あなたのおかげで、本たちが安心して眠れるね」
いたずらを叱るのではなく、子どもの「やってみたい」という力を、優しく育てていけたら…。その瞬間から、子育てはぐっと楽しくなっていきます。
まとめ いたずらの奥にある「力を育てるチャンス」
子どものいたずらには、「やってみたい」「自分の力を使いたい」というサインが隠れています。
叱る代わりに寄り添う視点で見つめることで、子どもを成長をサポートすることができます。
毎日の子育てに、ちょっとした視点の変化を加えてみませんか?