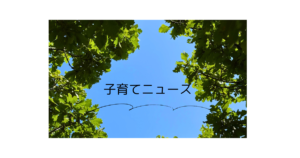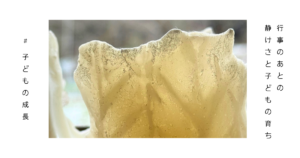「性教育」と聞くと、「知識を伝えること」を思い浮かべるかもしれません。たとえば、体の仕組みや生理、避妊などの知識を子どもに教えることが大切だと考える方も多いでしょう。
でも、シュタイナー教育における性教育は、知識だけを伝えるものではありません。子どもの感情を育て、思いやりの心を深めることを大切にしています。
知識だけでは本当の意味での「性の大切さ」は伝わりません。相手を尊重し、自分も大切にする気持ちが根づいてこそ、性に対する健全な価値観が育まれるのです。
では、どのようにして子どもの思いやりの気持ちを育てていけばよいのでしょうか?シュタイナー教育の視点から、そのヒントをお伝えします。
シュタイナー教育の性教育 思いやりの気持ちを育てる
シュタイナー教育では、「思いやりの気持ちを育てること」が性教育の本質と考えられています。
「相手の気持ちを大切にしなさい」と言葉で伝えても、実際に優しさを持てるかどうかは、その子の心の成長しだいです。知識を教えるだけではなく、感情を育てることが重要なのです。
たとえば、誰かが悲しい思いをしたとき、その気持ちを想像し、寄り添うことができるかどうか。これこそが、思いやりの気持ちの核となる部分です。
思いやりの心を育てるためにできること
子どもに「思いやりを持ちなさい」と言葉で伝えるだけでは、なかなか実践にはつながりません。では、どのような方法で思いやりの心を育てていけばよいのでしょうか?
① 子どもの「悔しさ」や「悲しさ」に寄り添う
思いやりの気持ちを育てるためには、子どもが失敗したり、悔しい思いをしたときこそチャンスです。
子どもがうまくいかずに落ち込んだとき、「大丈夫!」と励ますだけではなく、その気持ちにしっかりと寄り添ってあげましょう。
「悔しかったね」「頑張ったけどうまくいかなかったね」と言葉をかけ、一緒に気持ちを味わう時間を作ることで、子どもは「自分の気持ちを受け止めてもらえた」と感じます。
こうした経験を積むことで、他者の気持ちにも共感できる心が育っていきます。
② 絵本やお話を通じて、感情を育てる
シュタイナー教育では、「物語の力」をとても大切にしています。
物語の登場人物が悲しい思いをしたり、困難を乗り越えたりする過程を知ることで、子どもは自然と相手の気持ちを想像する力を育てていきます。
例えば、思いやりの気持ちを育むのに適した絵本として、以下のようなものがあります。
- 『フワフワさんは けいとやさん』(樋勝 朋巳):失敗してしまったフワフワさんを受け入れる優しさが描かれています。
- 『どうぞのいす』(香山 美子 著, 柿本 幸造 絵):森の動物たちの他人を思いやる心を感じることができます。
日常的に、思いやりの気持ちを大切にした絵本を読み聞かせることで、子どもが「相手の気持ちを考える」きっかけをつくることができます。
まとめ
シュタイナー教育における性教育は、単なる知識の伝達ではなく、思いやりの心を育てることに重きを置いています。
・ 知識だけではなく、感情を育てることが大切
・ 子どもの悔しさや悲しさに寄り添うことで、思いやりの心が育つ
・ 物語を通して、感情を豊かにする経験を増やす
今日の小さな関わりが、未来の大きな優しさにつながっていきますよ。