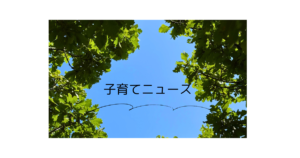小さな子どもが叩いたり噛んだりする場面に遭遇すると、つい声を荒げたくなります。でも幼児期には「自分のしたこと」と「相手の痛み」を結びつけられないことが多く、まずは「落ち着かせる」ことが最優先です。今回は現場で使える具体的な手順と声かけをわかりやすくまとめました。
なぜ子どもは叩いたり噛んだりするのか
1〜2歳ごろの子どもは、まだ言葉で自分の気持ちを表現したり、行動の結果(相手が痛がる)と自分の行為を結びつけたりする力が未熟です。「試してみたい」「どかしたい」「言葉が出ない」といった動機で、手が出てしまうことが多く、必ずしも「意地悪」や「挑発」ではありません。
現場でまずやること 落ち着かせる(実践3ステップ)
STEP 1:安全確保と身体の介入
- まずは被害を受けた子の安全を確保(抱き上げる/距離をとる)。
- 暴力を振るった子の興奮が強い場合は、厳しい叱責ではなく「手を添える」など身体で静める。ぎゅっと閉じた拳に手を添え、いっしょに開いてあげると効果的です。
- 短時間で効果が出る方法 深呼吸を促す、水を一口飲ませる、静かな抱っこや背中をさする。
STEP 2:静まったら気持ちを言葉にする
興奮が落ち着いたら、大人が落ち着いた声でそれぞれに寄り添いながら気持ちを引き出します。
- 行為を簡潔に伝える:「今、〇〇くんはおもちゃを取ろうとして手が出たね」
- 行為の背景を推測して言葉にする:「おもちゃが欲しかったんだね」
- 被害側の気持ちも促す:「〇〇ちゃんは痛かったね。どう感じた?」
STEP 3:次の行動を一緒に練習する
言葉で受け止めたあと、どうすればよかったかを一緒に実践します。親が代わって「伝え方」「頼み方」の見本を示し、子どもと一緒にやってみることで学習が深まります。
- 「次はこう言ってみようね」と親が率先して代弁する。
- 子どもが実際に「入れてもらう」「貸してもらう」場面を作り、褒める。
- できたら必ず肯定的フィードバック(短く、具体的に)。
注意点 これは深刻なサインかもしれない場面
次のような場合は専門家に相談を検討してください。
- 暴力が頻回である/年齢に比して過度に激しい
- 相手を傷つける重度の行為が繰り返される
- 家庭内に重大なストレス要因(虐待・トラウマなど)がある疑いがある
疑問があるときは、保育士・小児科・心理士・児童相談所など専門窓口に早めに相談してください。
まとめ
幼い子どもの「手が出る」行為は、発達段階の一部であり、まずは安全確保→身体的に落ち着かせる→気持ちを言語化→代替行動を学ばせるという流れで対応するのが効果的です。
親が静かに手を添えることは、子どもの中にある「社会性の芽」を守り育てるやさしい介入になります。今日もし同じ場面が訪れたら、まずは深呼吸を一つ。あなたの落ち着きが、子どもの安心につながります。