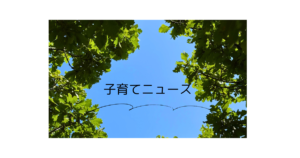子どもがルールを破るたびに、「どうして言うことを聞けないの?」と悩むことはありませんか?
でも実は、子どもの年齢によってルールを破る理由はまったく異なります。
特に10歳ぐらいからは、親の声よりも友達との関係が行動に大きく影響する時期。
今回は、そんな年齢特有の背景とともに、ルールを「自分のもの」として育てる声かけのコツをご紹介します。
10歳以降になると、子どもは「友達との関係」が最優先に
幼児期は「ルールを忘れてしまう」「衝動的に動いてしまう」といった理由でルールを破ることがありますが、10歳ごろになるとその理由は少し変わってきます。
この年頃になると、「親にどう思われるか」よりも、「友達にどう見られるか」が大切になってくるのです。
たとえば家ではルールを守れるのに、友達と一緒だと破ってしまう。
そんな行動が見られたとき、頭ごなしに叱っても伝わりにくいのです。
子どもがルールを「自分ごと」として捉えるための関わり
①まずは感情ではなく事実を聞き出す
子どもがルールを破ってしまったとき、「どうしてそんなことしたの!」と感情的に言いたくなる気持ち、よくわかります。
でもまずは、状況を静かに聞くことから始めてみましょう。
たとえば校区の外に出てしまった場合なら、「どうして外に出たのかな」「誰が誘ったのかな」「そのとき、どう思った?」といった質問で、子どもの内側にある動機を引き出します。
②「どうしたら思い出せるかな?」と一緒に考える
「それはダメでしょう!」と一方的に言うよりも、「どうしたら次は思い出せるかな?」と一緒に考える時間がとても大切です。子どもが「自分の意志で」ルールを守ろうとする第一歩になります。
③「親の言いつけ」ではなく、「自分の目標」に
親が決めたルールではなく、自分自身の中に納得できる理由があること。それが、行動を変える一番の力になります。
「自分がどうありたいか」を大切にした対話を、ぜひ重ねてみてください。
ルールを守れない=悪い子 ではありません
ルールを破るという行動の裏には、「試してみたかった」「どうすればよかったかわからなかった」といった葛藤があります。
叱る前に一呼吸置いて、「この子は何を大事にしようとしていたんだろう?」と寄り添うことができたなら、それは信頼関係を深めるきっかけになるはずです。
まとめ ルールは「押しつけ」ではなく、「育てていくもの」
子どもが成長するにつれて、ルールとの向き合い方も変わっていきます。
10歳以降は「他者の目」を意識し始める時期。親の役割は、ルールを押しつけることではなく、子どもがそれを「自分の価値観」として引き受けていくサポートをすることです。
「どうしてルールを破ったの?」ではなく、「どうしたら次に守れるかな?」と、心の奥にそっと灯りをともすような関わりを。 子どもは、その灯りを頼りに、少しずつ自分の道を見つけていきます。