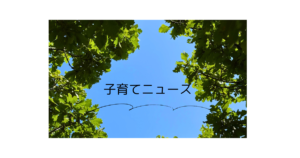「うちの子、算数が苦手みたいで…」
そんなとき、つい計算ドリルをたくさんさせてしまいがちですよね。
でも、シュタイナー教育では、算数をただの「正解探し」にはしません。
大切なのは、子どもの“考えるプロセス”と“感じる心”。
この記事では、シュタイナー教育における算数の教え方と、家庭でできる実践のヒントをご紹介します。
「答え」を教え込まない理由
シュタイナー教育では、算数力を単なる計算力ではなく、子どもの心と身体、感性、思考力すべてと結びついた力として育てていきます。
例えば「1+5=6」よりも、「6はいくつといくつに分けられるかな?」と問いかけて、
「1+1+1+1+1+1」「2+4」「3+3」「2×3」など、多様な視点で考える力を伸ばします。
間違いは「ダメなこと」ではない
子どもが「8=9+?」と答えてしまったときも、「あ、ちがうよ」ではなく、
「8=9−1ならぴったりだね!」と声をかけてみましょう。
答えは1つじゃないということを、体感的に学んでいくことが、子どもの安心感と意欲につながります。
家庭でできるシュタイナー的な算数の学び方
- 「8=◯+◯」のように、自由に答えを考える問題を出してみる
- おはじきや積み木を使って、目で見て数を体感する
- 料理の分量や、買い物のお釣りを数えるなど、日常で「数」に親しむ
シュタイナー教育が大切にしていること
算数は、「やらされるもの」ではなく「数を通して、世界とつながる感覚」を育む手段。
子どもにとって最初に出会う「数」の体験が、楽しく、安心できるものであることが、何より大切です。
正解を教え込むのではなく、「考えるって楽しい」と感じられる学びを、一緒に育てていきましょう。
まとめ
シュタイナー教育の算数では、正解よりも、感じる力と考える力を大切にします。
答えを覚えさせるのではなく、数に親しみ、探究する力を育てていく。
家庭の中でも、声かけひとつ、問いかけひとつで、子どもの算数への印象は大きく変わります。
ぜひ、今日から「数っておもしろいね」と一緒に楽しむ気持ちを大切にしてみてください。