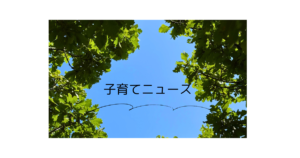子どもが「パンが欲しい!」「おもちゃが欲しい!」と言ったとき、親はつい「どうするべき?」と迷ってしまいます。でも、小さな子どもの「ほしい」は、実は必ずしも「手に入れたい」という意味ではないことがあるのです。今回は、子どもの「ほしい」の本当の意味を理解し、親子のコミュニケーションをより豊かにする方法をご紹介します。
子どもの「ほしい!」にはいろんな気持ちがある
子どもは言葉の使い方がまだ未熟なため、ひとつの言葉に多くの意味を込めています。「〇〇が欲しい!」と言ったとき、実際には次のような気持ちが隠れていることがあります。
- 考えているだけ:「パンのことを思い出したよ」
- 興味がある:「パンって面白そうだな」
- 安心したい:「ママが気にかけてくれるかな」
子どもは言葉で説明するのが難しい分、自分の気持ちを「ほしい」という言葉にまとめて表現しているのです。
「本当に欲しい?」と聞く前に気持ちを受け止める
子どもが「〇〇がほしい」と言ったら、まずは「本当にいるの?」と聞くよりも、その気持ちを受け止めてあげましょう。
💡 具体的な声かけの例
- 「パンのことを考えていたんだね」
- 「パンが気になったんだね、面白いね」
- 「パン、好きなんだよね」
このように、子どもの気持ちを代弁してあげることで、子どもは「自分の気持ちをわかってもらえた」と安心します。
「ほしい!」に振り回されないための対応法
「ほしい!」が続くと、つい「ダメ!」と否定したくなるもの。でも、子どもの気持ちを受け止めてあげると、「ほしい!」の嵐が少しずつ落ち着きます。
✅ 対応のコツ
- 子どもの気持ちを受け止める言葉がけをする
- 一度落ち着いたら、本当に必要かどうかを話し合う
- その場で与えられない場合は、「あとでね」と未来の約束をする
気持ちを受け止めると親子の関係がもっと穏やかに
子どもの「ほしい!」に振り回されず、まずは気持ちを受け止めてあげることで、子どもは安心感を持ち、親子の信頼関係が深まります。
✅ ポイントまとめ
- 子どもの「ほしい!」は、必ずしも物を求めているわけではない
- 気持ちを代弁してあげるだけで、子どもは安心する
- 落ち着いた後で、本当に必要かどうかを話し合う
まとめ:子どもの「ほしい!」に寄り添うことで心が通じ合う
子どもの「ほしい!」の言葉の裏に隠れた気持ちを理解してあげると、親子の関係がより穏やかになります。ただ物を与えるだけでなく、気持ちを受け止めて言葉にしてあげることで、子どもは安心し、親への信頼感も育まれていきます。